アインシュタインらしいおしゃれな名言
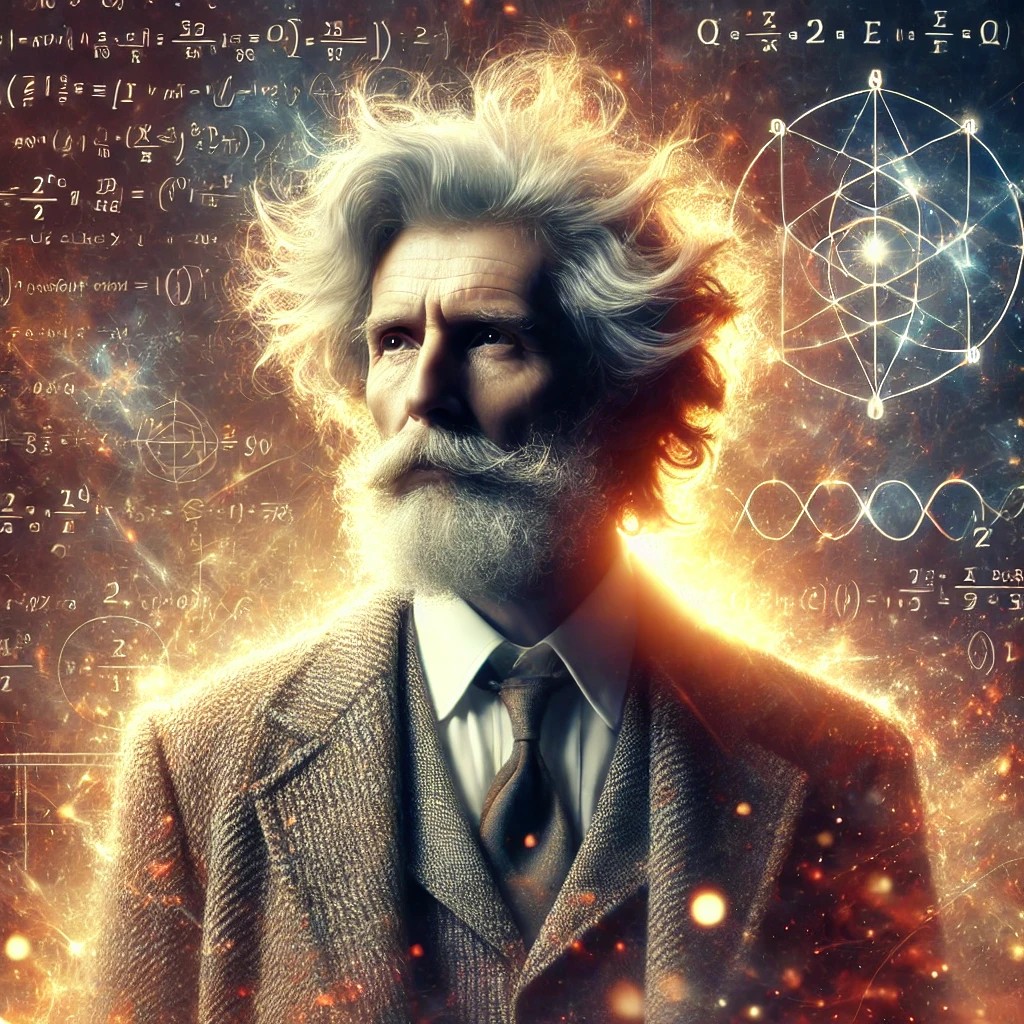
常識とは18歳までに身に付けた偏見のコレクションである
知らないうちにめんどくさい人になっていませんか?私は大人になるにつれて偏見は少なくなってきましたが、10代の頃は偏見のかたまりだったと思います。笑
アルベルト・アインシュタインが残したとされる言葉に、「常識とは、18歳までに身に付けた偏見のコレクションである」というものがある。この言葉は、私たちが無意識のうちに持っている「常識」というものが、実は個人の経験や環境によって形作られた偏った見方に過ぎないということを示唆しています。
私たちは、生まれてから18歳になるまでの間に、家庭、学校、地域社会、メディアなどからさまざまな価値観を学ぶ。その過程で、「これは正しい」「これは間違っている」「こうすべきだ」「こうしてはいけない」といった観念が植え付けられる。それらは社会を円滑に生きる上で重要な指針となるが、一方で、必ずしも普遍的な真実ではなく、その環境特有のルールである場合も多い。
例えば、日本では「電車の中で静かにするのがマナー」とされているが、国によっては電車の中で友人と賑やかに話すことが当たり前の文化もある。また、ある国では「左手で食事をするのは失礼」とされるが、別の国ではそのようなルールは存在しない。このように、「常識」とされるものは、視点を変えれば単なるローカルルールや偏見に過ぎないことが多い。
アインシュタインの言葉が示唆するのは、私たちが「常識」として受け入れていることを、一度疑ってみることの大切さです。18歳までに身に付けた価値観は、あくまでその時点での環境によるものであり、それが絶対に正しいとは限らない。新しい環境に触れたり、多様な人々と交流したりすることで、それまでの「常識」が単なる思い込みだったと気づくこともある。
科学の進歩もまた、この「常識の疑い」から生まれる。かつては「地球は平らである」「太陽が地球の周りを回っている」といった考えが常識だったが、それを疑い、検証し、新たな発見を積み重ねたことで、現代の科学が築かれてきた。同様に、社会の価値観や道徳観も時代とともに変化し続けている。
私たちが生きる上で、「常識」に従うことは必要な場面も多いが、盲目的に信じるのではなく、それが本当に正しいのか、自分の考えに合っているのかを問い直す姿勢が重要です。そうすることで、より広い視野を持ち、他者との違いを受け入れ、多様な価値観を尊重できるようになるでしょう。






コメント